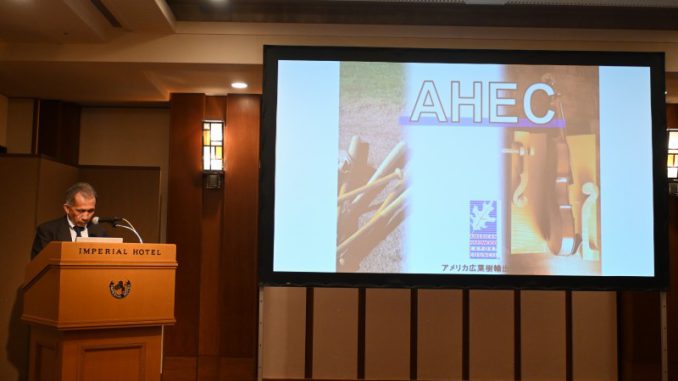
アメリカ広葉樹輸出協会(AHEC)が、「アメリカ広葉樹インテリアデザイナーセミナー」を、2024年11月26日に帝国ホテル東京で開催した。

冒頭では、AHEC日本代表の辻隆洋氏が挨拶したのち、米国大使館農産物貿易事務所所長のエリック・ハンセン氏が挨拶した。そののち、3つのテーマに沿った講演が実施された。

講演(1)では、AHEC日本代表の辻隆洋氏が「アメリカ広葉樹の合法性、持続可能性と環境への対応」をテーマに講演した。同氏は現地視察(国内)や、アメリカでのプレスミッションなどを実施していることや、米国の広葉樹の分布図を説明。米国では自然交配で広葉樹林が成長していることなど、アメリカ広葉樹と環境についても説明した。米国では人工衛星を使用して、広葉樹の蓄積量を集計しており、広葉樹の立木量は120~130億立方メートル分と、伐採量を大きく上回る成長量となっていることを明かした。
また、アメリカ広葉樹の約8割は個人農家の所有であること、レッドオークの立ち木量は東南部に多いことなども説明。チェリー、ハードメープル、ウォルナット、多様な樹種についての概要を語った。このほか、欧州森林破壊防止規則(EUDR)に対する対応策についても説明。第三者機関によるライフサイクルアセスメントを行っているとし、2025年3月末を目途に記者会見を開催予定であることを明かした。

講演(2)では「私と木とのつきあい方」をテーマに、TAO建築設計代表の川村弥恵子氏が登壇。
同氏が手掛けてきた事例を解説した。広葉樹を好む理由として、広葉樹は堅い点、色の選択肢が幅広い点、木目の美しさといった要素を挙げた。家具の設計も手掛けてきた同氏だが、「家具の精度はミリ単位。建築とは気にする単位が違う。その精度で建築も考えられるようになった。ミリ単位で検討するようになった」と話す。

木とうまく付き合うコツとして川村氏は①極端な環境におかないこと(温度湿度の観点)②留めないこと(固定しないこと)③濡らさないこと――を挙げながら、「木が求める環境は、人間が求める環境に近いのでは」と私見を述べた。サッシにホワイトアッシュを使用する理由は、①針葉樹と比較して、糸面でシャープな形状であること②オリジナルの断面形状加工が可能であり、ミリ単位の加工ができること➂木目の美しさ、高級感がポイントであることを語った。

講演(3)は、「府中の箪笥メーカーのアメリカ広葉樹との出会い」をテーマに、若葉家具の井上隆雄社長が講演した。冒頭では府中家具および若葉家具のこれまでの歴史を説明。2007年からにアメリカ広葉樹と出会い、製品づくりのプロジェクト「エコ・ファニチャープロジェクト」で、デザイナーの小泉誠氏とともに府中・大川のメーカーが手掛けていった。プロジェクトの目的は、節や白太、色違いなどの素材の有効活用であり、製品化することで継続的な取り組みに変えていくことを目的として取り組んだ。

井上氏はアメリカ広葉樹の出会いからの変化について、「アメリカ広葉樹と出会う前は、素材はナラやタモが主流で、広葉樹2割ほどしかなかったが、今はほぼ9割が広葉樹。ものづくりについてもタンスからリビング・ダイニング家具へ幅を広げることができた。素材の力でものづくりが変わり、デザインを加えることで、提案の範囲も変わった。作り手、社員の気持ちも変わっていった」とし「プロジェクトでは、節やしらたを使う家具の難しさ、今までとは真逆の製品となり、顧客への説明なども必要であることの難しさがあったが、しかし今はその個性が受け入れられるようになってきており、SDGsのように素材の有効活用としての価値観も受け入れられるようになってきている」と語った。
セミナー終了後はレセプションが開かれた。開会挨拶は国際建材・設備産業協会の鮫島修二会長、閉会挨拶は日本フリーランスインテリアコーディネーター協会の江口惠津子会長が務めた。





